外苑前にある建築家会館大ホールで開催されている『香山壽夫ドローイング展』。10/15に始まったこの展示会は、10/24まで開かれている。短い会期の展示会は気づいたら終わってしまっていることが多いので、気を付けたい。ここで展示されているドローイングはどれも圧倒されるような、精密さを兼ね揃えたものばかりで驚く。また、会場に入ってすぐの場所に展示されている「建築家のドローイング」からの引用文は身に染みるものだった。『「描くこと」が世界の認識に繋がる必要な所作であること』、『描くことは線を選ぶこと』、『建築家は、設計している限り、建築について考えている限り、たえずドローイングをつくっているのである』、文章自体は巨大な紙を4枚にわたる長文で引用され展示されており、展示が始まるとすぐに引き込まれてしまった。(学生の必読書といわれる所以を再認識した。展示と合わさることで説得力が並大抵ではない。)

本展は、4つの層に分かれて構成されている。A.「かたちの混沌」、B.「選び取られた線」、C.「たちあがる空間」、D.「風景が生まれる」といった4層は、それぞれ一つの建築が出来上がる過程で描かれる、多種多様なドローイングの根底にあるものを表している。そして、その様々な段階におけるドローイングが渦を巻くように展示されるといった構成になっている。

たとえば、「かたちの混沌」では、建築家の意識がはじめて紙に表出した瞬間とととらえ、スケッチから図面になりかけているもの、概念図までを分け隔てることなく混在した場として展示している。B.「選び取られた線」ではスタディ過程のドローイング、C.「たちあがる空間」では実施図面でのドローイング、そして、D.「風景が生まれる」では建築が風景の一部となっているさまが描かれ、また、A.「かたちの混沌」へと回帰していくことが伝えられる。



展示されているドローイングはどれも魅力的でかつ、線を引くときの緊張感が直に伝わってくるものだった。引用した文中で、CADで線を引かない理由にも触れていたが、線が迷いなく点と点を結んでおり、人がもつ迷いが起こらないという部分が腑におちた。たしかに、香山さんが言うように、CADは時間がかからず便利であるが、線を引く過程での思考はカットされている。むしろ、形を作った後にそれを見比べて形を選ぶような思考の方法だろうか。この変化には、常に意識的にならないといけないと思う。線を引くことへの責任がなくなって、だれが作った建築なのかが分からなくなっていく気がした。

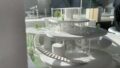

コメント